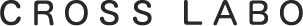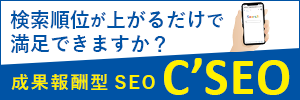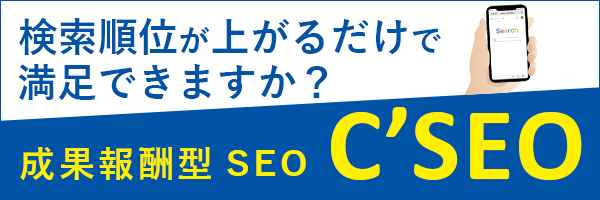SEO対策を学ぶにお勧めの本厳選11選
2025/02/05 SEOSEOの基礎SEO対策WEBマーケティングコンテンツマーケコンテンツマーケティングライティング内部修正内部対策外部対策書籍
WEBサイトを運営している方はもちろんのこと、WEBマーケティングに関わる方やコンサルティングに関わる方も、そしてこれからその業界で働く方やサイト制作・運営を自身でしようと思っている方にとってSEO対策を学ぶことは非常に意義があることです。
これだけSNSをはじめ情報(サイトやアカウント)が世にあふれている時代に単にWebサイトを作っただけでは、多くの人に知ってもらうことは難しい時代。SEO対策は、そんな状況を打破し、Webサイトを成功に導くための強力なツール(手段)なのです。
ただ、SEO対策は大事と思っていてもSEO対策に関する基礎知識がなければ現状把握はもちろん何から取り組むべきかもわからなくなってしまいます。
(当社のクライアント様からもそんな声をよく聞くようになってきたので今回記載します)
ということで今回はSEO対策の全体像や基礎がわかる本、実践的な知識が得られる本の2カテゴリに分けてお勧めの本をご紹介!!
※実際に当社に新たに入社した方にも必ず読んでもらっています。
目次-Contents-
SEO対策を学ぶ意義
そもそもSEO対策を学ぶ意義やメリットって何でしょうか?
簡単に羅列してみました。
1. より多くのユーザーにリーチできる
SEO対策を行うことで、検索エンジンで自社のWebサイトが上位表示されるようになります。
これは、潜在顧客が商品やサービスを探す際に、最初に目に触れる機会を増やすことは集客力向上に繋がります。
2. ターゲット層に合わせた集客が可能
SEO対策では、検索キーワードを戦略的に選定することで、特定のターゲット層にピンポイントでアプローチすることができます。
検索して求めている人は前のめりの方です。
そんな形アプローチができるのです。
3. 広告費の削減
SEO対策は、有料広告と比べて長期的に見ると費用対効果が高いと言われています。
一度上位表示されれば、継続的な費用をかけることなく、安定した集客が見込めます。
広告費を削減し、他のマーケティング活動に予算を回すことも可能です。
4. ブランドイメージ向上
検索結果の上位に表示されることは、ブランドイメージ向上にも繋がります。
信頼性が高く、専門性の高い企業として認識され、顧客からの信頼を獲得することができます。
5. 競合との差別化
SEO対策は、競合他社との差別化を図るための有効な手段です。
競合他社がまだ手がけていないキーワードで上位表示されることで、競合との差別化を図り、自社の強みをアピールすることができます。
6. Webサイトの改善
SEO対策を行う過程で、Webサイトの構造やコンテンツの質を見直す必要があります。
この過程を通じて、ユーザーにとってより使いやすい、より魅力的なWebサイトへと改善することができます。
7. 長期的な視点でのマーケティング
SEO対策は、一朝一夕に効果が出るものではありません。継続的な取り組みが重要です。
SEO対策を通じて、長期的な視点でマーケティング戦略を立てることができるようになります。
また、個人レベルでもSEO対策を学ぶことは、単なるスキルアップだけでなく、ビジネスの成長を加速させるための自己投資と言えるでしょう。
SEO対策の基本・基礎が学べるオススメ書籍
まずはSEO対策の概要や基礎・基本がわかる本をご紹介!
いちばんやさしい新しいSEOの教本 人気講師が教える検索に強いサイトの作り方
著者:安川 洋、江沢 真紀、村山 佑介
2014年2月に出版された「いちばんやさしい新しいSEOの教本 人気講師が教える検索に強いサイトの作り方」。
SEO対策の基本ともいえるその目的からSEO対策による効果検証をする方法までを著者の皆さんがわかりやすく解説している書籍です。
一番最初に読む本として難しすぎずSEO対策の全体が掴めます。
検索にガンガンヒットさせるSEOの教科書
2008年6月に出版された「検索にガンガンヒットさせるSEOの教科書」。
帯に伝説のバイブルとまで書かれている本書は出版から17年たった今でも基本を学ぶバイブルとなっています。
実際当社代表の岡本がWeb業界に入った16年前に一番最初に読んだ本(らしいです笑)
この本を読んだうえで最新のSEO対策の情報などを見るとその遍歴も理解することができるのできます。
10年つかえるSEOの基本
2015年に出版された「10年つかえるSEOの基本」は検索エンジンとSEO対策の関係性を重視しつつ、その本のタイトル通り10年使えるSEOの考え方を学ぶことができます。
より実践的なSEO対策の知識が学べるオススメ書籍
次は先述の本を読むことで理解できた基礎知識をより実践的に学ぶことができる本を以下のカテゴリに分けてご紹介します。
- ・実践知識全体が学べる
- ・内部対策(内部修正)に重点を置いた実践知識が学べる
- ・番外編(ライティング)が学べる
に分けてご紹介!
実践知識全体が学べる書籍
SEO対策 検索上位サイトの法則52
2013年12月に出版された「SEO対策 検索上位サイトの法則52」は内部対策(内部修正)・外部対策を含むSEO対策はもちろん、逆にやってはいけない(ペナルティになる可能性がある)SEO対策までを解説している書籍です。
著者自身、アフィリエイトサイトを複数運営している方なのでこれからご自身でアフィリエイトなどを考えている方には特に勉強になると思います。
現場のプロから学ぶSEO技術バイブル
2018年7月に出版された「現場のプロから学ぶSEO技術」はサイト構造やhtml構造、サイトの速度向上、モバイル対応なども踏まえ、よりGoogleに評価されやすいWEBサイトにするための内部対策(内部修正)・外部対策・コンテンツSEOまでが網羅された書籍です。
WordPressで加速させる!ソーシャルメディア時代の【新】SEO戦略マニュアル
2011年12月に出版された「WordPressで加速させる!ソーシャルメディア時代の【新】SEO戦略マニュアル」はWordpressのサイトを考慮し、キーワード選定やコンテンツ対策・内部対策(内部修正)・外部対策はもちろん、Wordpressでのサイト運営のコツまで記載された書籍です。
WordPressでサイト運営をしているのであれば一度読んでおくべき書籍といえます。
2024年11月に出版された「強いSEO “SEOおたく”が1000のサイトを検証してわかった成果を上げるルール」はサイトのタイプ別に戦略や実際の施策をまとめた超実践的な本です。
また、実践的な施策のために必要なSEOの地頭を鍛える思考法なども記載しています。
大規模サイトやECなどのにも対応しているのでそんなサイトの運営に関わる方は是非読んでおきたい一冊です。
内部対策(内部修正)に重点を置いた実践知識が学べる書籍
これからはじめる SEO内部対策の教科書
著者:瀧内 賢
2012年s10月出版の「これからはじめる SEO内部対策の教科書」 は昔から一貫して変わらないとされているSEO対策の内部修正の中でもhtmlのコード見直しについて重点が置かれた実践向きの書籍となります。
著者:瀧内 賢
2022年2月に出版された「これからのWordPress SEO 内部対策本格講座」は先述のこれから始めるSEO内部対策の教科書を記載した著者がWordpressのサイトにフォーカスして内部対策(内部修正)について記載した書籍です。
WordPressでのサイト運営者やそれにかかわる方には有用なカスタマイズなどが実践的に記載されています。
番外編(ライティング)が学べる書籍
最後に番外編として、SEO対策の中でも手法の1つであるコンテンツのライティングに関する書籍をご紹介
SEO対策のための Webライティング実践講座
著者:鈴木 良治
2015年2月に出版された「SEO対策のための Webライティング実践講座」はSEO対策の基礎知識のおさらいからコンテンツライティングの際の注意点までが記載された実践向け書籍。
効果的なキャッチコピー・コンテンツの制作方法はもちろんアクセス解析からコンテンツの改善を探る方法までが記載されています。
沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—〈SEOのためのライティング教本〉
著者:松尾 茂起
2016年11月に出版された「沈黙のWebライティング – Webマーケッター ボーンの激闘 – 〈SEOのためのライティング教本〉」はコンテンツ制作においてどのように文章を書けばいいか、狙ったキーワードの順位を上げるためにどのようなテキストや要素を書けばいいかなどがわかる書籍です。
是非、SEOに関わるライターさんには読んでおいてほしい書籍です。
なお、本書籍は「沈黙のWEBマーケティング – WEBマーケッター ボーンの逆襲(ディレクターズエディション)」がシリーズ化された二版目の書籍となります。
まとめ
SEO対策は、Webサイトの成功に不可欠な要素です。
たとえるならば高層マンションの骨組みや基礎工事といったところでしょうか。
SEOを学ぶことで、より多くのユーザーにリーチし、ブランドイメージを向上させ、最終的にはビジネスの成長に貢献することができます。SEO対策は、Webサイトの運用者にとって、今や必須のスキルと言えるでしょう。
SEO対策は、決して難しいものではありません。
様々な情報やツールが提供されており、初心者でも学ぶことができます。
まずは、基本的な知識を学び、少しずつ実践していくことが大切です。
是非様々な書籍をしっかり読んで勉強することで対象のサイトの立ち位置や目指すところ競合との過不足などを見極めてサイトの成長につなげていきましょう。